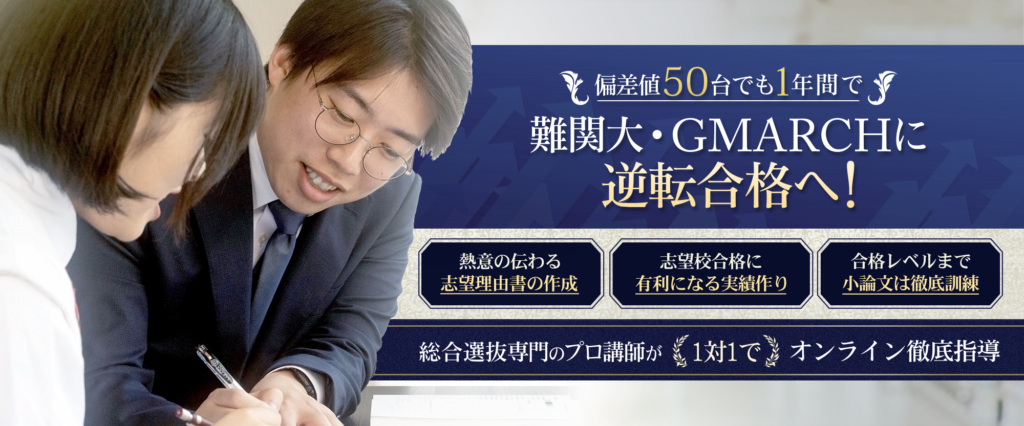指定校推薦と総合型選抜は性質が似ているため
両方準備しよう、受けようかなと思っている人は多いと思います。
合格している人って、どんな人?
自分でも合格できるかな?
具体的にどんな試験が実施されているの?
という疑問がわいてきますよね。
ここでは、青山学院大学 文学部 史学科の指定校推薦について、合格した人はどんな人なのか、そして、実際の試験はどんな内容だったのか紹介します。
そして、指定校推薦、総合型、一般受験の対策をどのように並行して行っていたかもご紹介します。
複数の受験形式を並立受験する人に参考になる情報が詰まっているので、是非参考にしてくださいね。
目次
青山学院大学 文学部 史学科の指定校推薦の出願・選抜要件(2024年度入学試験)
| 専願 | 評定平均 | 履修要件 | 既卒要件 | 共通テスト | 語学試験や検定試験 | 試験内容 |
| 専願 | 評定平均4.1以上 | 条件なし | 現役生のみ | 不要 | 不要(評価はする) | 志望理由書(A41枚) 1次試験枚) 1次試験 与えられた歴史に関する課題に対して簡単なレポートを書く 2次試験:個人面接(20分程度) |
青山学院大学合格者のプロフィール
| 名前 | T.H |
| 受験年度 | 令和6年度(2024年度)入試 |
| 受験大学 | 青山学院大学文学部史学科合格 筑波大学人文科学類比較文化二次試験辞退 |
| 進学大学 | 青山学院大学文学部史学科 |
| 現役・既卒 | 現役 |
| 性別 | 男性 |
| 出身高校 | 東京都 私立 偏差値62 |
| 通っていた塾 | 早稲田塾 |
| 評定平均 | 4.2 |
| 共通テスト成績 | 282点(英国歴のみ)70.5% |
| 学力レベル | 高校では上の中 青山学院の判定はCくらい |
| 英語資格・検定 | 英検2級 |
| その他の資格 | 全国高校生英作文コンクール入賞 |
| 留学経験 | なし |
| その他特筆すべき活動 | 高校での探究活動 |
志望校選び ― 研究テーマの設定とそれとの合致
―総合型選抜を受験したきっかけは何ですか?いつ頃から準備を始めましたか?
幼い頃から歴史が好きで歴史の学習漫画や大河ドラマを食い入るように見ていた子供でした。ただの好きであった歴史が探究のテーマとしてハッキリしたのは2016年の熊本地震がきっかけでした。当時熊本に住んでいた友人が被災し、現地の状況や熊本城が被った被害を見て人の生活や文化に大きな傷跡や影響を残す災害に興味を持ち、災害の歴史を研究したいと考えるようになりました。高校生になったタイミングでずっと取り組んでみたかったレポートの作成を始めました。当時は受験のことは特に考えずに好きだから行っていました。そこから具体的に総合型受験を決めたのは高校2年生の2月でした。
総合型の受験にあたっては複数の大学を受けることにし、私立大学では学習院大、中央大学、國學院大学を受けようと決めていました。国立では筑波大学のAC入試(アドミッションセンター入試)に興味を持っていましたが、筑波大学のAC入試は求められることから半ば受けることは諦めていました。しかし、塾の先生から筑波大を受けると他の大学の対策が楽になると言われ、その理由としては、
・AC入試においては1次試験において9000〜20000字程の本格的なレポートの提出が求められるが、筑波大学用に一つ書き切ってしまえば他の大学への志望理由やレポートにそれを活かせること。
・一度レポートを作るのは自身の中で今までの自主探究活動を纏めて整理することにも繋がり、面接で話すことがし易くなる。
ということを教えていただきました。
対策方法 ― 早いうちからの一般対策で総合型対策との並立を
―入試に向けての対策スケジュールを教えてください
1、2年生の頃は苦手な理系科目を中心に提出物や自主課題に積極的に取り組み、評定が下がらないようにしていました。長期休みにはミニレポートの作成や財団のレポートコンテストに応募などしていました。高校1年生の夏休みに司馬遼太郎記念館が行っている司馬遼太郎フェローシップに明治期の新撰組隊士に関するレポートを書いて応募しました。2年生の夏休みは災害史に関する簡単なレポートの作成、これは受験のレポート作成の基礎になりました。加えて、その年の全国高校生英作文コンクールに応募して入賞を頂きました。
一般入試の勉強は2年生の秋頃から少しずつ始めました。GMARCHの文学部の過去問を中心に、2年生の学力でも解けそうな国語の長文読解や日本史の問題を解いていました。2年生のうちに過去問を解き始めるのは少し早い気もしますが、文系で国語、社会が得意な方なら少しずつ解き始めておけば3年生になる前に志望校の問題に慣れることができて良いと思います。私は1週間ごとに大問単位で解いて学校の先生に添削して貰っていました。3年生の4月から7月にかけては、各校の志望理由書の作成と筑波大のレポート作成、受験科目の基礎演習を並行して行っていました。また、青山学院の指定校推薦の申請も行っていました。こちらは校内での競争が予想されたので、期待半分くらいで総合型の準備をしていました。夏休みに入った後に、過去問演習も本格的に始めました。夏休み前に筑波大のレポート作成以外の書類作成は殆ど終わっている、という状況であったので夏休み中は一般受験の勉強に集中して取り組むことができました。面接練習は夏休み明け後に行いました。
―どうやって総合型選抜の対策をしましたか?塾などには通っていましたか?
高校3年生になる前のタイミングで早稲田塾に入塾しました。志望理由書の添削など、高校でサポートもしてもらえましたが細かいところやより専門的な意見が欲しいと思い入塾しました。また、早稲田塾は授業がオンラインだったので土日にもフォームを通じて先生に質問や訂正を受けれたのも心配性の自分には合っていたと思います。逆に高校のサポートが手厚い方は無理して塾に通う必要はないと思います。自分と同じで心配性の人は通いたくなるかもしれませんが、ご家庭とよく相談することをお勧めします。
実際に入試を受けて ― 探究の連続性は説得力に繋がる
―総合型選抜での挫折経験はありますか?
志望理由書を最初に書いた時には散々で構成や内容全てにダメ出しされてしまいました。何回もやり直している時に、自分のやってきたことは無駄だったんじゃないかと思ってしまう時もありました。4月から7月後半にかけて一校目の志望理由書を7回ほど書き直しました。
―自分はどうして青山学院大学に合格できたと思いますか?
早いうちから自主探究を始めていたのが良かったと思います。研究テーマの連続性が強く求められる史学においては一年生から自主探究を行っているというのは強い説得力に繋がります。面接で教授の方に「一年生から、このレベルのレポートに取り組んでいるのは良いですね。それが今の探究に繋がっているのが非常に分かりやすく、素晴らしい」と褒めて頂きました。校内選抜においても評定だけでなく、自分が一年生からレポートに熱心に取り組んでいるのを先生方に知って頂いていたので推薦をいただけたのだと思います。
大学生活 ― 総合&推薦合格者は高い専門性を持っている
―入学してみて、指定校推薦で合格した学生と一般選抜で合格した学生のカリキュラムなどに何か違いはありましたか?
入学した時の初回の課題に違いがありました。指定校推薦者は初回に課題図書を読んでの要約と自分の所感をまとめたレポートの提出を求められました。
―総合型選抜の合格者はどんな人が多いですか?
総合型選抜・指定校推薦者の合格者は高度な専門性や興味を持っている人が多いです。話していて、勉強になるし、とても楽しいです!!
青山学院大学文学部史学科の実際の試験内容、志望理由書の具体事例
―志望理由書や学習計画書にはどんなことを書きましたか?
災害が文化に与える影響や災害伝承の地域ごとの同一性や差異を検証することを探究テーマとし、それを今までどう研究して来たのか、大学でどの授業を受けて、どのように研究していきたいのかを書きました。また、学校推薦型入試の場合は集団での協調性やリーダーシップをアピールする文書も入れる必要があります。
・序論(探究内容に繋がる内容)→本論(探究内容とその為の大学での学習計画)→結論
このような形で一般的な総合型の志望理由書は構成されています。しかし、推薦型入試の場合は本論の後に
・本論②(高校時代の経験を元にした協調性やリーダーシップの重要性)
自分の場合はクラス委員の経験から集団でのリーダーシップや協調性が大事だと理解したというような内容
が入ってきます。
―学部の実際の試験内容について
記述試験では日本or世界の幾つかの文化財の例が挙げられ、それらを伝承・保護していくためにはどのような対策が考えられるかを記述する。面接では、志望動機、記述試験で書いた文書を元にした質問、高校時代の活動、高校時代の探究活動と進み、20分ほどでした。そのうち10分間が探究活動に関する質問でした。
―メッセージ
総合型選抜や指定校推薦、ここには挙げなかった公募推薦型選抜など年内入試の選択肢は多様化していっています。たくさんの人がその道を選択することで求められるスキルや経験も高くなっている中で、最後に自分の背中を押してくれるのは自分の好きや興味です。年内入試を受けるか迷っている人は自分がなぜその分野が好きなのか、興味があるのか、探究したいのかをよく考えて、少しでもトライしたい気持ちがあったら是非トライしてください!!自分がやってきた探究は友達や家族以上に力をくれます。心身には気をつけて頑張ってください、応援してます!