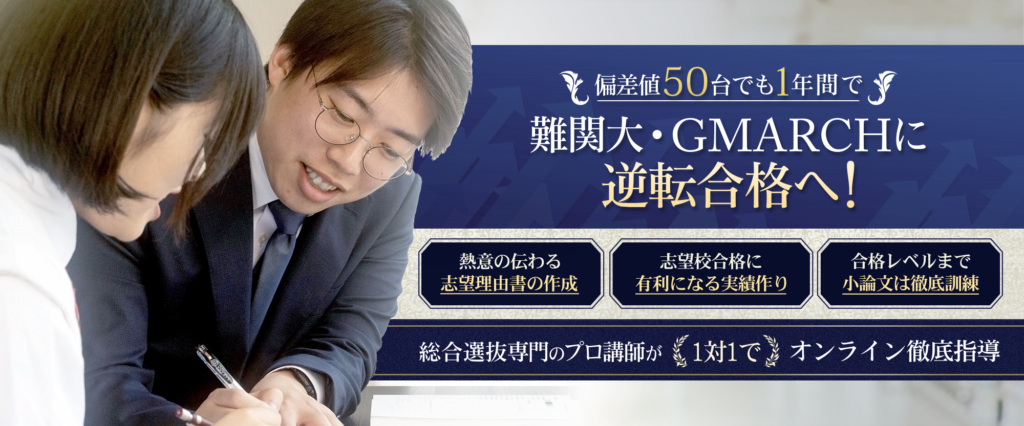最近は、国公立大学での総合型選抜が盛んに行われるようになってきました。国立大学では、全体の78%の大学が総合型選抜を導入しています。
その中には、「旧帝大」と呼ばれる大学も含まれており、特に東北大学では将来的に入試を総合型選抜に全面移行する方針を表明するなど、難関大学でも総合型選抜は急激に広まっています。
このような大学の総合型選抜は、大学での勉学・研究に必要となる学力を身につけたうえで、能力や人間性を求めるというしくみになっています。そのため、国際バカロレアや帰国子女といった特定の経験を出願要件に含まない、いわば誰でも挑戦できる総合型選抜が設定されています。
そのうえ、学力試験は一般選抜よりも受験科目数が少なく、文系科目に特化している場合がほとんどですので、得意科目と苦手科目の成績の差が大きい高校生でも、得意科目だけを使って国立大学を受験することができます。そのため、私立大学を中心に受験しようと考えている高校生も国立大学の受験にチャレンジしやすくなっています。
そこで、旧帝大の文系学部に総合型選抜で合格した現役大学生である筆者が、総合型選抜について分析しました。
本記事では、旧帝大だけでなく国公立大学、難関大学を目指す文系の受験生に向けて、文系学部に焦点をあてて総合型選抜の傾向と対策を紹介していきます。ぜひ最後までチェックしてみてください!
旧帝大の総合型選抜の傾向を知る
旧帝大で総合型選抜を導入している文系学部は以下の通りです。
| 大学 | 学部 |
| 東北大学 | 文・教育・法(AOⅡ・AOⅢ)経済(AOⅢ) |
| 京都大学 | 総合人間・文・教育 |
| 大阪大学 | 文・人間科学・外国語・法・経済 |
| 九州大学 | 共創・教育(Ⅰ方式)文・法・経済(Ⅱ方式) |
その他旧帝大では、北海道大学と名古屋大学が理系のみ総合型選抜を導入しています。また、東京大学、京都大学の一部の学部は学校推薦型選抜を導入しています。北海道大学総合文系入試でも「総合型選抜」という入試方式がありますが、国際バカロレアの認定が要件となっているため、本記事では割愛します。
各大学の出願要件を知ろう
まずは、各大学の出願要件や試験科目を見てみましょう。
以下のデータは、記事公開時点で各大学が公開している募集要項から引用したものです。
| 東北 AOⅡ | 東北 AOⅢ | 京都 | 大阪 | 九州 Ⅰ | 九州 Ⅱ | |
| 既卒要件 | 現役 | 現役or1浪 | 現役or1浪 | 現役or1浪(法のみ現役) | 現役or既卒5年まで | 現役or既卒5年まで(文)・現役or1浪(法・経済) |
| 共通テスト | なし | あり | あり | あり | なし | あり |
| 筆記試験 | あり | 教育のみ面接前課題論文あり | あり | 小論文あり(法・経済なし) | 共創のみ講義に対するレポートあり | 小論文あり(法のみ英語試験) |
| その他試験 | 面接あり | 面接あり | 教育のみ口頭試問あり | 面接あり(外国語のみ口頭試問) | 共創:討論・面接 教育:プレゼンテーション・面接 | 面接あり(文のみ英語面接) |
どの大学でも、学力や能力を評価するような試験と、言葉を交わして人間性や意識を評価するような試験という2つの要素が含まれています。上記の求める人物像にあった学生に入学してもらうため、重視する要素をそれぞれ評価するしくみです。
ここでは割愛しましたが、いずれの大学でも、志望理由書を提出することや、その大学・学部が第1志望であり、合格した場合に必ず入学することが条件になっています。その大学で学ぶ強い意欲のある学生を求めているのですね。
各大学の方針を見てみよう
続いて、各大学が掲げている総合型選抜の目的や求める人物像を見てみましょう。
学力と意欲を重視する東北大学
AO入試とは、詳細な書類審査と丁寧な面接等を組み合わせることによって、入学志願者の能力・適性や学習に対する意欲、目的意識等を総合的に判定する入試制度です。
東北大学の「AO入試」は、上記の制度に基づき、第Ⅱ期及び第Ⅲ期の2種類の入試方法があり、いずれも志望する学部の専門分野に強い関心を持ち、 東北大学を第一志望とする人を求めています。 また「優れた学力」を重視し、幅広い基礎学力と豊かな人間性を兼ね備えた人を評価します。
この選考では幅広い知識、技能を含む基礎知識や論理的な思考力・判断力・表現力、コミュニケーション能力等の学力とともに、豊かな人間性や創造力、発想力、倫理性、主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度、学問に対する好奇心などを評価します。学力については、一般選抜と同等以上の水準を求めます。
高大接続を重んじる京都大学
本特色入試では、高大接続と個々の学部の教育を受ける基礎学力を重視し、
①高等学校での学修における行動と成果の判定
②個々の学部におけるカリキュラムや教育コースへの適合力の判定
を行い、①と②の判定を併せて、志願者につき高等学校段階までに育成されている学ぶ力及び個々の学部の教育を受けるにふさわしい能力並びに志を総合的に評価して選抜します。
自主的な探究ができる人材を求める大阪大学
総合型選抜・学校推薦型選抜では、大阪大学の教育理念に共感し、単なる自己実現にとどまることなく、何のために学ぶのかを真剣に考え、それを実行できる学生の入学を期待しています。最先端の知を学び、自らも新たな知を生み出すとともに、それをどのように社会に活かすかという志と、その実現のためのスキルや知識も備えた人間、大阪大学が育成したいリーダー人材はこういう人なのです。
選抜においては、このような考え方を踏まえ、基礎的な学力については大学入学共通テストを利用して評価しますが、同時に高等学校等での学びの質や経験をきちんと把握し、総合的に評価することにしています。何よりも重視したいのが、「自分の頭で考える習慣」を持っているかどうかです。正解に素早くたどり着く能力よりも、一生を通じて出会うさまざまな問題に向き合い、考え抜く力が大事だと考えています。正解のない複雑な社会的課題に対して果敢に挑戦する志を持った学生の入学を期待しています。
感性や意志なども総合的に評価する九州大学
九州大学の総合型選抜は、従来の教科・科目の筆記だけによる学力試験とは異なり、「認知領域」と「情意領域」での能力を総合的に評価することに主眼を置きます。ここで、「認知領域」での能力は、知識や技能などの側面、具体的には問題発見能力、論理的思考力、論理的表現力、理解力、応用力などに、また「情意領域」での能力は、感性や意志などの側面、具体的には学習意欲や好奇心、探究力、責任感、誠実性、協調性などに現れるとされています。
具体的な選抜方法や評価方法は、それぞれの専門分野や特色に応じて求める学生像やアドミッションポリシーが異なりますから、実施する学部等によって違いますが、いずれも詳細かつ丁寧な論文試験や面接などを行い、ただ表面的な学力のみを見るのではなく、意欲や関心なども見て総合的に評価する選抜方式です。しかし、入学後の修学の基はやはり基礎学力ですから、それが必要なのは言うまでもありません。
これらの記述からわかること
どの大学も、「基礎学力」と「大学での学修・研究への志」が重視されていることがわかります。「優れた実績」などという記述はみられません。つまり、特別な実績の有無は問わず、大学が求めるレベルの学力と、大学での学びや研究、それを社会に活かしたいという強い思いがあれば、誰でも合格できる可能性があるのです。(太字:筆者)
旧帝大の総合型選抜対策
これを踏まえて、旧帝大の総合型選抜で合格するためには何をすればいいでしょうか。
※大前提、受験したい大学や選抜方法が決まっている人は、募集要項を必ずチェックして、出願要件や提出書類、試験内容を把握しておきましょう!!
旧帝大出願には評定平均最低4.3、可能な限り5.0に近づける
総合型選抜の中には、調査書の評定平均が4.3以上であることが出願要件になっているものがあります。しかし、総合型選抜に出願するのであれば、評定平均4.3で満足せず、可能な限り5.0に近づけることが必要です。
そのためには、普段の授業や定期テストの取り組みが優れていることを、高校で評価を担当する先生に認めてもらわなければいけません。
ということで、定期テストではなるべく高得点をとれるよう、普段の予習復習を欠かさず、毎回本気で取り組みましょう!
それでは、常に高得点をとるような成績優秀者でなければ出願要件すら満たすことはできないのでしょうか。そんなことはありません。筆者は高校3年間で赤点を数回とりましたが、評定平均は4.6でした。もともと総合型選抜の受験を想定していたわけではありませんが、手を抜けない性格であったこともあり、日々の小テストや授業への取り組みには特に力を入れていました。小テストは合格するだけではなくできるだけ満点をとれるように、通学のバスの中で小テストの勉強をしていました。
総合型選抜を受けるか決めていなくても、普段から真面目に取り組めば定期テストの点数のわりに評定が高くなることがあります。先生からの印象もよくなるので取り組んで損はありません!
大学でやりたい研究の意義を明確にする
まずは、「なぜその大学に進学しなければならないのか」を明確にする必要があります。また、旧帝大は学問というより研究に力を入れている場合が多いので、
「なぜその研究をしたいのか、しなければならないのか」
「その研究は、社会でどのように役に立つのか」
ということを、面接官である教員に納得してもらわなければなりません。これらが、志望理由書の主な内容になります。
この答えとしては、
・専門の教員がその大学で研究していること
・その分野で有名な大学であること
・大学がある地域が、その研究に適していること
などが挙げられます。
筆者は、自分の経験をもとに問題意識を明確にし、そのメカニズムとアプローチ方法を研究することで、自分のようにつらい思いをする人を少しでも減らしたいという思いがありました。また、その分野を専門としている教授がその大学にいらっしゃったため、その教授のもとで研究したいという旨を伝えました。
自分の手で研究成果を社会で活かすという将来像を描く
自分が大学を卒業したあとどのようにその経験を社会に還元するかといった将来像を描いておくことも重要です。大学は、研究に対する意欲の高い総合型選抜で入学した学生には、大学院に進学して将来の研究者になってほしいという思いがある可能性が高いので、自分の手で研究成果を社会で活かすという意思を示すことが大事です。一方で、知人は専攻を希望する分野の教員になりたいという旨を伝えましたが、大学の方針と少しずれていたこともあり、不合格となったそうです。社会に大きな影響を与えることが想定しにくい将来像を描いていた人は、不合格になる場合があるようです。
ただ、スポーツ推薦などとは異なり、入試の段階で志望した分野に入学後に必ず進まなければいけないということはありません。大学に入学してからさらに興味のある分野を見つける人もいます。今の希望を叶えなければならないというプレッシャーがある人もいるかもしれませんが、気負いすぎなくて大丈夫です。目標は高い方がいいですよ!
旧帝大にかかわらず、総合型選抜全般に共通することですが、志望理由書は遅くとも3年生の初夏までには書き始めましょう!2年生の秋頃から書き始めた人もいるようです。筆者も志望理由書を書きながら興味のある分野を見つけていったので、早めに書き始めてたくさん添削してもらって時間をかけて磨き上げるのが効果的であると思っています。最低でも5回、できれば10回以上添削してもらうようにしましょう。たくさん書き直しを命じられて心が折れそうになることもあるかもしれませんが、「なにくそ!」「絶対に諦めないぞ!」と思って喰らいついていくことで、この大学に進学したいという思いがどんどん強くなります。筆者が総合型選抜に挑戦したのは、打たれ弱い自分の性格を変えるという目的もありました。メンタルは相当強くなりました!
一般選抜より難しいことを想定して過去問演習をする
筆記試験の対策としては、過去問を解くことはもちろんですが、一般選抜の過去問を解くことがよい対策になります。前述の通り、旧帝大の総合型選抜は基礎学力が重視されており、入試に使う科目については一般選抜と同等以上の学力水準が求められます。問題の出題形式も一般選抜と近いことが予想されるので、それらを解き、復習することで求められる水準の学力を保つことができます。
また、総合型選抜は一般選抜と比較して最新の社会問題に関する問題が出題される傾向があります。筆者は自宅で講読していた新聞を読んだり、就活生向けのニュース解説サイトを見たりしていました。その他、高校で時事問題を取り上げた英語長文読解の問題集が配られたので、それを解き直すこともありました。出題された問題がニュースで見たことのある内容だと概略をつかみやすいので、筆者は時事問題を結構楽しんで解いていました。
長文読解を正確に解くには、難しい単語を正確に訳す力が求められるので、英単語はしっかり身につけておきましょう。筆者は単語帳をめくってもなかなか覚えられませんでしたが、1年生の頃から毎日続けていた英単語アプリのおかげで、本番に単語でつまずくことはありませんでした。自分に合った学び方を確立させることも大切です。
ただ、大学によっては論文を書いたりプレゼンテーションをしたりする選抜もありますので、これらは過去問を参考にしながら練習を積みましょう。
練習を積んで臆せず思いを伝えられるようになる
面接の内容に関するものでは、
・師事したい教員が執筆した、研究したい分野の論文を読む
・関係する分野の新書を読む
・志望理由書に書いた内容に関する質問には、何を訊かれても確実に答えられるようにする
・学業に関係のないことでも、大学に入学したら挑戦してみたいことを考えておく
ということが重要です。
いくら自分の関心のある分野といっても、面接官である教員はその道を追究しているプロです。間違った認識があれば考えの浅さがバレてしまいます。志望理由書を書く段階から、その分野において研究されていることや世の中の流れについては周辺知識も含めて把握しておきましょう。大学での研究でも、先行研究を踏まえるというのは重要視されています。
また、面接そのものに関しては、
・大人の圧力に慣れる
・基本的な面接マナーは無意識でできるようにする
・いろいろな大人に面接官になってもらって練習をする
・とにかく練習回数を積む
というのが効果的です。
大学教授は思った以上に大人の圧力があります。しかも、本番は面接官が複数いることも多く、専門家に囲まれた状態で自分の思いを伝えなければならないこともあります。誰しも知らない大人と向き合うと緊張してしまうので、まずは大人の目を見て、自信をもって話せるようになりましょう。大学入試で初めて面接を経験する人も多いと思いますので、練習を積み重ねて、面接という場の雰囲気に慣れておきましょう。特に面接のマナーは、面接官に与える印象を左右する重要な要素になります。本番、緊張した状態でも礼儀正しい印象を与えられるよう、入退室のマナーや流れは無意識にできるようにしておくと安心です。就職活動でも役に立ちますよ。
筆者のおすすめは、自分のことをまったく知らない先生に面接官役になってもらい、練習をすることです。これは筆者が通っていた高校での面接練習の方針でした。自分に関する事前情報が志望理由書の内容しかない状態の大人に対して、自分がどれだけその大学で研究したいのか納得してもらうための伝え方を学ぶうえでとても参考になりました。特に強面の男の先生や、管理職の先生との練習は面接の雰囲気さながらで緊張しましたが、その経験が本番のプレッシャーに打ち勝つ要因にもなりました。教育関係者の場合、入試に関する有益な情報を提供してくれたり、自分の入試を応援してくれたりと、味方を増やすこともできます。
総合型選抜を受験する仲間と高め合おう
このほか、私がやってよかったと思うことは総合型選抜を受ける仲間とつながることです。総合型選抜を受ける場合、一般選抜を受ける人より早く受験モードに入って対策をする必要があるので、周りの人が志望校を決めていなかったり部活動を熱心に行っていたりする中で、他の人とは異なる勉強をしなければなりません。周囲の雰囲気に振り回されたり、一般選抜よりも受験の情報が手に入りにくかったりして不安を感じてしまうかもしれません。そんな時に、受験校や学部にかかわらず、総合型選抜を受ける仲間が近くにいると、志望理由書作りの大変さを共有したり問題を教え合ったりと、高め合い、励まし合いながら頑張ることができます。筆者は、受験への不安を抱える中で彼らの存在が心の支えになっていました。
総合型選抜の対策・練習の目安は、「本番会場で『私はこんなに頑張って対策したんだから受かるはず!』と自信をもてる程度」だと思っています。「私が入学したら絶対に大学にとってプラスになります!」と言えるくらいの自信をもって試験に臨んでください。学問に対する強い思いをもった入学志願者は、きっと大学から歓迎されるはずです!