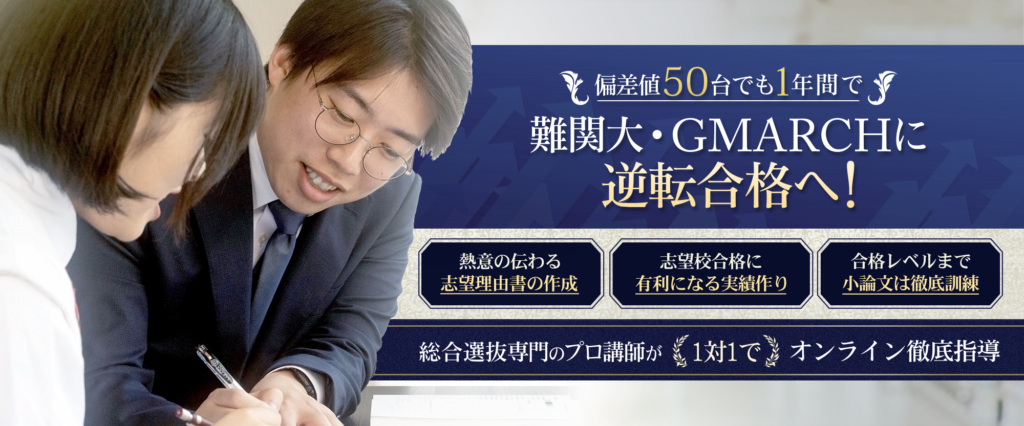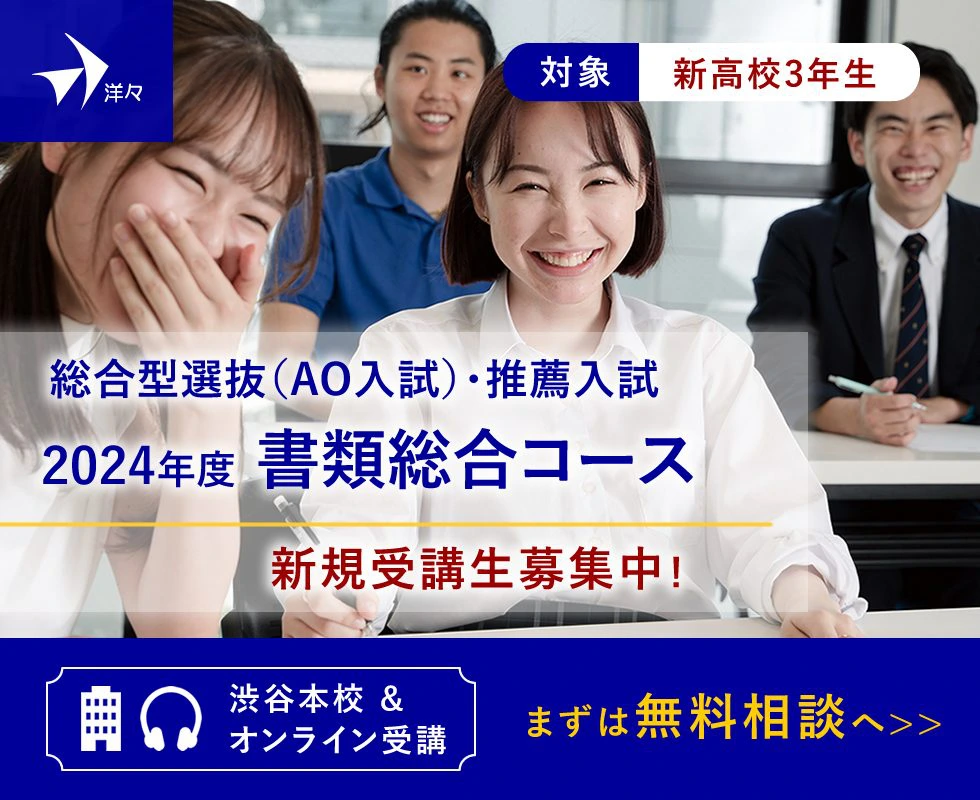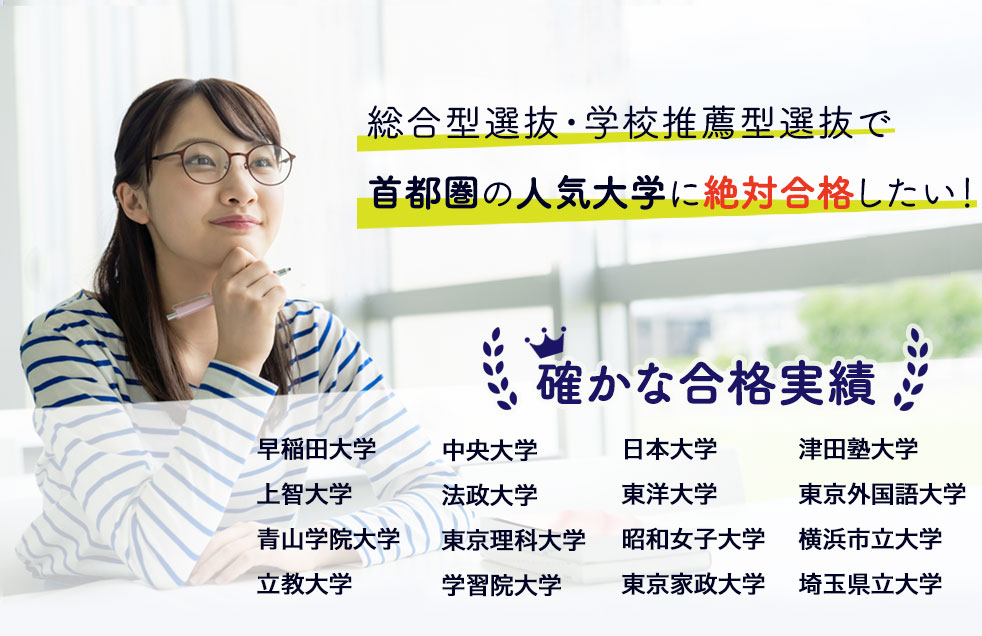総合型選抜を受験する際、必ずといっていいほど必要になるのが志望理由書です。志望理由書では、「なぜ他の大学ではなく、受験した大学に入学する必要があるのか」を面接官である教授たちに伝えなければなりません。しかし、面接官は数多くの志望理由書を読むため、単に「○○の分野に興味があるから」といった内容で終わらせてしまうと、印象に残らず、その大学に入学したい思いが伝わりにくくなってしまうことがあります。
その中で、筆者は「自分の原体験を活かして大学で研究したいことを明確にする」という流れで志望理由書を書きました。その結果、出願書類の点数が100点中92点と、かなり高い評価を得ることができました。
本記事では、筆者自身が「原体験」「過去の経験」を活かして志望理由を練り、東北大学の総合型選抜を突破した経験をもとに解説していきます。
目次
友人関係トラブルをきっかけに発達心理学に興味を抱いた
筆者は教育学部(教員養成課程ではなく、教育学や教育心理学を研究する学部)を受験し、その中で教育心理学・発達心理学を専攻することを希望しました。その理由として、思春期・青年期の他者との関わりに特徴的な同調行動の発生メカニズムや、それを起因とするトラブルを防ぐ教育的取組について研究したいということが挙げられます。
このような志望理由となった背景には、小学校高学年の時に経験した学校での友人関係トラブルがあります。それまで仲の良かった友達が急にグループで行動するようになり、いつでもそのメンバーで一緒にいて他の人たちとは関わらなくなるという状況になりました。筆者はそれになじめなかったことで嫌がらせを受け、学校生活がつらくなってしまいました
このように、思春期特有の友人関係によるトラブルに苦慮している先生方は数多くいらっしゃいます。筆者のようにつらい思いをする子どもを一人でも多く減らし、子どもたちが人と関わることに楽しさや喜びを感じられるような教育的環境をつくることに貢献したいと考え、これを志望理由のメインテーマとしました。
自分に大きな影響を与えた原体験を思い出そう
志望理由にしやすい原体験には、以下のようなものがあります。
- いじめ・犯罪など社会問題に関わった経験
- 家族の病気・障害など身近な人に起こったこと
- 自分に大きな影響を与えた大人の存在(医師・カウンセラーなど)
- ボランティア・課外プログラムでの活動
単に「科学館に行った」「授業で学んで興味をもった」というような生活の中での経験だと、大学の志望理由につながる原体験としてはインパクトが薄いかもしれません。志望理由になりうるものとしては、自分の生き方や学問的関心に大きな影響を与えた経験がふさわしいでしょう。
また、その時の詳細、そこでどのように感じたか、何を考えたかも思い出し、原体験の詳細を明確にしておくと、後々志望理由を構成するときに役に立ちます。
原体験の「モヤッと」が解決された未来を描こう
原体験の「モヤッと」したことを文章化する
上記のように自分にとってインパクトのある経験をすると、「あのとき、どうしてあんなことが起こったのだろう?」「先生がおっしゃっていた〇〇についてもっと知りたい!」というように、なにかモヤッとした気持ちが生じることがあります。
このように、その経験を通して興味をもったことや疑問に思うことが見つかったら、それを文章で表してみましょう。
筆者の原体験をもとに「モヤッと」を文章にしてみると、
- なぜあのとき友達は急にグループで行動するようになったのだろう?
- なぜ自分は友達と同じように行動しなかったのだろう?
- なぜこの違いによって、自分は嫌がらせを受けたのだろう?
というようになります。
「モヤッと」を解決したら、社会にどんないいことがあるか考える
ここからは、原体験から感じたことを志望理由にふさわしい文章にする過程に入ります。
志望する大学での研究は、この「モヤッと」を明確にするためのものになります。しかし、それをそのまま面接で伝えると、個人的な疑問を解消するために研究をしたいのではないかと捉えられてしまいます。
総合型選抜では、「なぜその研究をしたいのか、しなければならないのか」「その研究は、社会でどのように役に立つのか」ということを自分の言葉で伝え、それを面接官である教員に納得してもらわなければなりません。そこで、この「モヤッと」が解消されることの社会的意義を見出します。
筆者の場合は、もっとも大きな思いとして「自分のように、思春期・青年期特有の友人関係に起因するトラブルによってつらい思いをする子どもを減らしたい」というものがありました。ここから発展させると、この「モヤッと」が解消されることの社会的意義として、
- 思春期・青年期の子どもが同年代とより良質な関係を築けるようになり、心身の健康につながる
- 思春期・青年期の子どものストレス要因の減少につながる
- 学校教員や施設職員など、思春期・青年期の子どもたちと関わる大人が子どもたちにより適切なアプローチをすることができる
- 集団でのトラブルを未然に防ぐ教育システムやプログラムの開発につながる
- 同年代の集団でのトラブルが減ることにより、いじめや不登校の減少につながる
ということが期待できます。
社会的意義というと難しく聞こえるかもしれませんが、「自分と同じような経験をした人にどうなってほしいか」「自分と同じようなつらい思いをする人を減らすためにはどうすればよいか」といった問いにすると取り組みやすくなります。
「モヤッと」を専門分野とする学問分野を見つける
最後に、それを追究するために究める必要のある学問分野を定めます。この時のポイントは、
- 分野の名前だけでなく、その中で主に着目すべき要素を見つける
- その学問を研究している研究者が属している大学を見つける
ことの2つです。
例として、筆者の場合は、
発達心理学の中で、学齢期の子どもを対象とし、主に社会性や道徳感情に着目している。また、その分野を専門とする教授が、志望する大学に所属して研究している。
という要素がそろっていたことから、志望校を確定させました。
これらを定めるには、自分の「モヤッと」に関係する論文や新書を読み、自分の関心のある分野を執筆している研究者を見つけることが必要です。論文は「CiNii」や「Google Scholar」などのウェブサイトで検索できます。これらは大学生になってもよく使うウェブサイトです。
志望理由書に書いたものは面接で詳しく問われることが想定されるので、事実に基づいたことを書きましょう。「経験が先にあって、そこからこのテーマについて研究したいと思った」という流れで専攻を決定することが重要です。くれぐれも、インパクトのある経験を作り上げたり、自分がインパクトのある経験をしたからといって興味もないのに関連した分野を志望したりすることのないように!
原体験を志望理由書に取り込むメリット
- 他の受験者との差別化を図れる
- 研究したい内容とつなげやすい
- 大学で研究したい思いを強く表しやすい
自分の体験をもとにその大学で研究したいという思いは、その受験者特有のものです。経験から学んだこと、そこから興味のある研究テーマを見つけたこと、そしてそれがどのように社会に活かせるか想定すること、という流れで志望理由書を構成することができ、その大学で研究したいという思いがより伝わりやすくなります。
さらに、自分が経験したことがもとになっていると、その経験に対する思い入れがあるため、必然的に大学で研究することに対する思いが強くなります。それが面接官にうまく伝われば、その熱意が評価につながるかもしれません。
もちろん、その研究テーマを研究したい大学が受験校なのかを明確にすることは必須です。
まとめ:経験・原体験を活かした志望理由を作成する順序
①自分に大きな影響を与えた経験・原体験の詳細を思い出す
②原体験の中の「モヤッと」した部分を文章化する
③「モヤッと」を解決したら、社会にどんないいことがあるか考える
④「モヤッと」を専門分野とする学問分野を見つける
この順番は、そのまま志望理由書の構成になります。筋の通った志望理由は、その大学に入学して研究したいという強い思いを他者に伝えるうえでとても役に立つものになります。さらに、そこに自分の経験をうまく持ち込むことで、他の受験者との差別化ができ、面接官の印象に残る受験者になれる可能性もあります。自分ならではの経験を武器にして、志望校に入学したいという強い思いを存分にアピールしましょう!