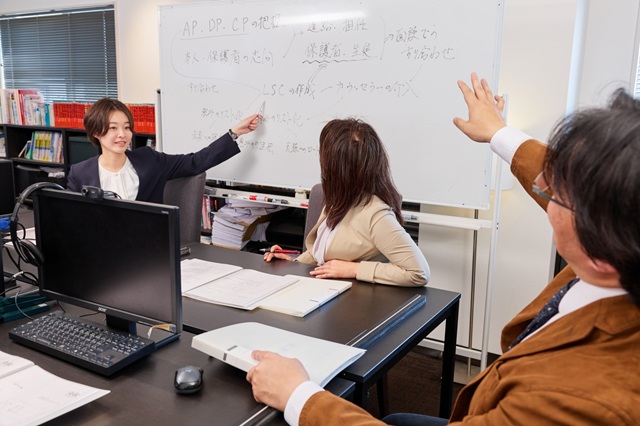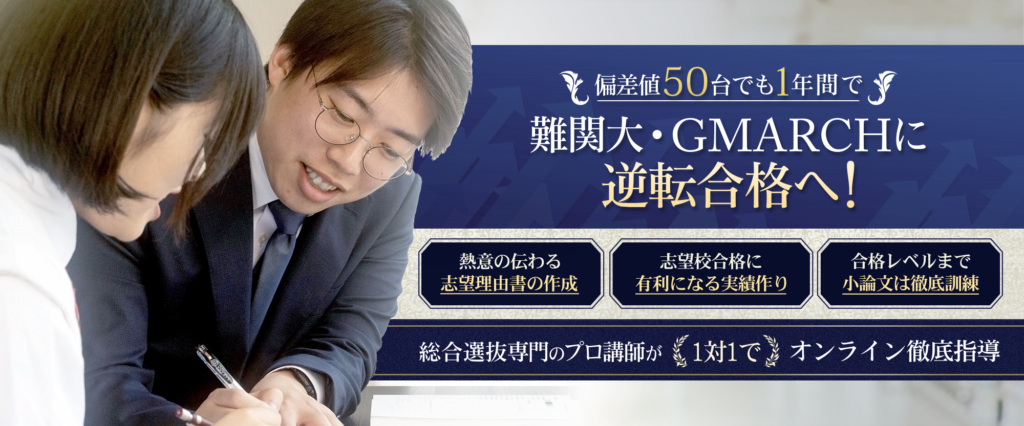はじめに(座談会参加者の紹介)
「総合型入試は、成績だけではなく、総合的な評価に基づいて合否を決める…」
確かにその通りです。
ただ、成績(評定値)も合否に大きく関わっていることも事実。
今回は、ソゴセバサーチを運営している現役の進路指導のベテラン達が、それぞれの経験から「各学校に必要な大まかな評定値」を赤裸々に語ります。
学年末評定の目標設定の目安にして下さい。
今回のリモート会議参加者(名前は仮名)
中川先生:
都内中堅進学校の進路指導部所属。厳しい指導を心がけているが、「それも役割分担。私は嫌われ役。受かればいいんです」と断言する熱血漢。
浜田先生:
北関東中堅進学校の進路指導部所属。4人の中では最もベテランで、唯一の50代。30年入試の最前線を張ってきたため、知識も豊富。
宇野先生:
都内上位進学校の進路指導部所属。特に国公立や私立上位校の入試事情に精通していて、進学者も多いことから実体験に基づいたデータも豊富。
荻野先生:
南関東の上位進学校の進路指導部所属。4人の中では一番の若手だが、進路指導部主任の右腕として日々多忙を極める。「9月から11月?地獄ですね」とのこと。
評定値は絶対ではないが最重要
中川:
まずは、読者の皆さん向けに前提になる言葉について簡単に説明をしておきたいと思います。
評定は、一般的に定期テストの「素点」と、授業態度や提出物、小テストなどから算出される「平常点」の合算を、100点満点に換算した値によって決まります。
基準は学校によって異なりますが、一例としては85点以上が5、70点以上が4、50点以上が3、30点以上がが2、それより下になると1となる、などがあります。
一般的な9月~10月出願の総合型入試なら、1年生と2年生の学年末評定、3年生の1学期までの評定の平均値が、「評定値」として調査書に記載されます。
浜田:
基準は学校によってばらつきがあるのであくまで目安ですね。うちは少し違います。
中川:
総合型入試は評定値だけではないという話もありますが、本音を言えばどうですか?
私は正直なところ、評定値が最重要だと思っています。
宇野:
他の実績があれば評定値が多少低くてもひっくり返せるとは思いますが、やはり重要だと思います。
結局のところ、その生徒の能力を測る一番確実な指標ですからね。
大学も、入学しても勉強についてこられないという事態を防ぎたいでしょうし。
荻野:
評定値が低くても合格を取れた事例はありますが、正直な事を言うと「順当」な結果が多いですね。
まあ、高くても落とされたケースもありますし、絶対的な基準ではないと思いますが。
浜田:
志望理由書や小論文などで大逆転!ということは無くはないですけどね。
今は、総合型入試の対策は学校だけではなく専門塾も増えてきているので、時間と手間をかけてしっかり対策した生徒が逆転したというケースもあります。
[編集部コメント]
先生方の意見では、評定値は絶対的な要素ではないが、総合型入試で合否を左右する最重要要素という認識のようです。「総合型入試は成績だけではない」とはいえ、最低限の評定値はないと、合格の難易度は跳ね上がるということですね。
続いては、実際にいくつくらいの評定値が必要なのかという話題に入ります。
評定値は、GMARCHや国公立なら4.3欲しい
中川:
確かに、対策をしっかりするのは今後、総合型入試の大前提になってきそうですね。
ちなみに、皆さんの見解では、どのレベルの大学でだいたいどれくらいの学校なら戦えるという手ごたえがある評定値はありますか?難しいかもしれませんが、そういうテーマの座談会ですし、できれば…。
(一同苦笑い)
荻野:
結構難しい質問ですよね。うちは、GMARCH以下を受験する生徒が割と多いですが、私の経験では、GMARCHなら最低ラインとして4.0は超えていてほしいですね。4.3あれば不利にはならないかなという印象です。日東駒専なら、最低でも3.8は欲しいです。まあ、学部によってやや数字はブレますが、生徒にはそれくらいは目指してほしいと言っています。
浜田:
立教の異文化コミュニケーションだと、4.0はきつくないですか?
荻野:
ですね。偏差値60を超えてくると、4.0は結構リスキーです。異文化コミュニケーションは65なので、4.3以上はないと厳しい印象はあります。
浜田:
日東駒専も割と幅がありますよね。
荻野:
そうですね。日大の文理学部辺りだと、偏差値45~55くらいですが、偏差値55なら最低でも3.8はあってほしい。偏差値45なら、3.6でも戦えるかな?という印象はありますね。
宇野:
学部によってばらつきはありますから一概には言えないですが、早慶上智なら最低でも4.3、できれば4.5以上欲しいですね。
国公立はかなりばらつきがありますが、旧帝大なら4.5以上は最低限、それ以外でも4.3くらいは欲しいですね。医学部はちょっと別として、他の学部ならそんな感じじゃないですか?
公立なら、もう少し低くても戦えるところはありますが、それでも4.0は欲しいですよね。
中川:
4.9以上になると印象はだいぶ変りますから、そこを目指してほしいですよね。
浜田:
高いに越したことはないですが、それは要求が高すぎます(笑)
4.9はなかなかいないですね。学年トップクラスですから、そういう子は偏差値が高い大学にトライしてほしいところです。
中川:
昔に比べて少し、要求される評定値が高くなっているような気もしますね。
荻野:
それは言えているかもしれません。かつての推薦入試に比べて募集枠も増えましたが、一方で受験者数も増えたので結果的に要求される評定値は上がったのでしょうね。
[編集部コメント]
評定値の目安としては、日東駒専なら3.8、GMARCHなら4.0、国公立やGMARCHでも偏差値が高い学部は4.3…というのが目安になるようです。偏差値が65を超えてくると4.3は必須ということですが、4.3は殆どの教科が5か4ということになります。かなり頑張らなくてはいけないですね。
つまり、「成績が不十分でもワンチャン受かる」という意識で取り組むのはかなり危ないと言えそうです。
最後に

総合型入試での合格を目指すためには、まず「日々の積み重ね」の結果である評定値を高くしておくことがかなり重要だということがわかりましたね。
確かに総合型入試は「成績だけではない、本人の特性や課外活動なども総合的に考慮して合否を出す」入試ではありますが、だからと言って評定値を軽視していいわけではありません。
評定は1年学年末、2年学年末、そして大抵は3年1学期までの成績が加味されています。
1年生はまだ進路が決まっていないから備える必要はない、ではなく、総合型入試は1年の定期試験からその戦いが始まっているとも言えそうです。
今回、先生方の座談会の中でかなり具体的な数字が出てきました。
関東圏の先生方だったので、関西の学校の話が出ていませんでしたが、偏差値と照らし合わせると目安になりそうですね。
是非、目指す評定値の参考にしてみて下さい。